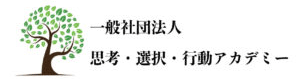なぜ「相談してくれない部下」に悩むのか?
「もっと早く言ってくれればよかったのに……」トラブルやミスが起きたあとで部下の状況を知り、そんな言葉を口にしたことはありませんか?
部下が困っているのに相談してこない。上司としては「なぜ黙っていたのか」と不思議に思う一方で、彼らには彼らなりの理由があります。多くの場合、それは「やる気がない」からではなく、心理的な不安や職場の環境要因が重なっているのです。
この記事では、部下が相談しない背景を心理・組織・コミュニケーションの3つの観点から整理し、若手マネージャーが“相談される上司”へと成長するための実践的なヒントをお伝えします。
相談してこないのは「やる気がない」からではない
部下が相談を避ける3つの心理的要因

評価されることへの不安
部下にとって「相談=弱みを見せること」になりやすいのです。特に昇進や評価が近い時期ほど、失敗や迷いを見せるのを怖がります。心理学ではこれを“評価懸念”と呼び、人は他者に無能だと思われることを強く避ける傾向があります。
この壁を壊すには、日頃から「早めの相談はプロの仕事」と明言しておくことが大切です。上司が“相談=成長の一歩”という文化を発信すれば、部下は安心して声を上げられるようになります。
上司の反応への恐れ
過去に「それくらい自分で考えろ」「また同じこと?」といった反応を受けた経験があると、それが心のブレーキになります。表情や言い方ひとつで、「また怒られるかも」と思い込んでしまうのです。
話を聞くときは、まず「教えてくれてありがとう」「なるほど、そう思ったんだね」と受け止めましょう。たった一言でも、安心感は大きく変わります。
“自立”の誤解
特に20代の若手は、“上司に頼る=甘える”と感じやすい傾向があります。しかし本来の自立とは、必要に応じて助けを求められる状態のこと。自分一人で抱え込むことではありません。
上司から「困ったら早めに共有してくれたほうが助かる」と繰り返し伝えることで、「頼る=責任ある行動」と認識を変えることができます。
上司が無意識にかけている「圧力」
部下が相談しづらくなる要因の一つが、上司自身が放っている“無意識の圧力”です。たとえば、忙しそうにパソコンを見ながら「で、結論は?」と急かす。眉間にシワを寄せたまま話を聞く。これだけで部下は「今は話しかけないほうがいい」と感じてしまいます。
また、会話の中で「なんでできなかったの?」という“詰問型の質問”も要注意です。代わりに「どこで詰まってる?」「どう感じた?」と問いかけるだけで、会話の温度が変わります。相談は“安心”の上にしか成り立ちません。最初の反応を変えるだけで、部下の行動が少しずつ変化していきます。
「相談できない環境」が生まれる職場の構造
プレイングマネージャーの多忙化が生む“話しかけにくさ”
若手マネージャーの多くは、プレイヤーとしての仕事も抱えています。そのため常に忙しく、部下から見ると「今は邪魔したくない」「後で話そう」と気を遣わせてしまうのです。この“話しかけにくさ”が続くと、部下はタイミングを逃し、相談を後回しにします。やがて「もう自分でやってしまおう」と思い込み、問題を抱え込むようになります。
忙しい時期こそ、「話していい時間」をあらかじめつくることが重要です。たとえば週に一度、10分だけ「最近どう?」と声をかける時間を設ける。短くても“相談できる場所がある”という安心感が、チーム全体の風通しを大きく変えます。
「結果主義」がもたらす“失敗を恐れる文化”
数字や成果だけが重視される組織では、失敗を報告することが「減点」と感じられます。結果だけを追い求めると、プロセス共有や相談が減り、「完璧な状態になるまで報告しない」風潮が生まれてしまうのです。
Googleの研究「プロジェクト・アリストテレス」では、チームが高い成果を出す最大要因は「心理的安全性」だと示されています。つまり、失敗や不安を共有しても評価されない安心感こそが、相談を促す鍵なのです。
失敗を責めるのではなく、「早く気づけてよかったね」と言える文化づくりから始めましょう。
心理的安全性が崩れたチームに現れるサイン
- ミスの報告が遅くなる
- 雑談が減る
- 同じ人だけが発言する
この3つが重なっているなら、チームの心理的安全性が下がっているサインです。一度“話しても大丈夫”という安心感を取り戻さなければ、相談は増えません。その第一歩は、上司が自分の弱みを先に見せることです。「私も最初はうまくいかなかった」「前回同じミスをした」と共有するだけで、部下は一気に心を開きます。
「相談される上司」に共通する3つの原則

①「話しても大丈夫」と思わせる“受容の姿勢”
相談しやすい上司ほど、部下の話を“評価せずに受け止める”姿勢を持っています。アドバイスや指摘よりも、まずは「聴く力」が信頼を生みます。心理学的にも、人は自分の話を否定せずに聴いてもらえるだけで、ストレスが軽減し、思考が整理されやすくなることが分かっています。
最初の一言を変えるだけで印象は大きく変わります。「それは大事な視点だね」「教えてくれて助かる」と伝えるだけで、“安心して話せる空気”が生まれるのです。
② 相談の前段階を拾う「雑談力」
多くの部下は、いきなり「相談があります」とは言いません。「最近ちょっとモヤモヤしてて」「この案件、うまくいくか不安で…」といった何気ない言葉が、相談の前触れです。ここで「大丈夫?」とひと言添えるか、「少し話そうか?」と声をかけるかで、その後の関係は大きく変わります。
雑談の中に埋もれている“小さなサイン”を拾う力こそ、相談される上司の共通点です。忙しい時期こそ、あえて数分の余白を設けましょう。コーヒーを淹れる時間、会議の前後の雑談など――ほんの数分の対話が、信頼関係を支える土台になります。
③ 相談後の対応が信頼を積み上げる
相談を受けた後の行動は、次の相談につながる“テスト期間”です。話を聞いたまま放置してしまうと、「話しても意味がない」と思われ、再び沈黙が戻ります。反対に、相談後に「その後どうなった?」「あの件、進展あった?」と気にかけるだけで、部下は「覚えていてくれた」と感じ、信頼が深まります。
また、上司が「話してくれたおかげで助かった」と伝えると、“相談すること自体が貢献”という認識に変わります。信頼は相談の“あと”に育つ。小さなフォローを積み重ねることで、部下は安心して次の一歩を踏み出せるようになります。
明日からできる!相談される上司への行動ステップ
ステップ①|週1回の「ミニチェックイン」を設ける
1on1のように構える必要はありません。週に1度、5〜10分だけ「最近どう?」と話す時間をカレンダーに入れておくだけでも十分です。「この時間は気軽に話していい」という枠を可視化すると、部下は相談のタイミングをつかみやすくなります。
また、この時間では“成果”よりも“感情”を聞くようにしましょう。「何がうまくいった?」「何が気になってる?」という2問だけでも、対話の質が変わります。
ステップ②|「どうした?」よりも「どう感じた?」で始める
相談を受けたときに、いきなり「何が問題?」と切り込むと、部下は防御的になります。それよりも「どう感じた?」「どんなところが気になる?」と感情を言葉にさせると、本音が引き出しやすくなります。
感情から入ると、事実の整理もスムーズに進みます。「なぜ?」より「どこで」「どう思った?」。この質問を意識するだけで、部下は安心して自分の考えを話せるようになります。
ステップ③|相談後のフォローで“安心”と“成長”を残す
相談を受けたあと、「教えてくれてありがとう」で終わらせず、数日後に「その件どうなった?」と声をかけましょう。
たとえ短い一言でも、“見てもらえている”という実感は部下の信頼を大きく高めます。
もし改善が進んでいたら、「早めに共有してくれて助かった」「このやり方、次も活かせそうだね」とフィードバックを添える。相談が“成長の場”に変わった瞬間、部下は自信を持って動けるようになります。
ケーススタディ|「相談してくれない部下」が変わった瞬間

若手マネージャーAさんのケース
昇進直後のAさん(32歳)は、プレイングマネージャーとして毎日多忙。部下からの報告が少なく、「最近何を考えているのか分からない」と悩んでいました。
ある日、顧客対応で大きなトラブルが発生。報告が遅れた理由を尋ねると、部下から返ってきたのは「忙しそうだったので言い出せなかった」という言葉。Aさんはショックを受けました。
その後、Aさんは週に1回の「5分チェックイン」を導入し、何気ない会話の中で「最近どんなことに悩んでる?」と声をかけるようにしました。最初のうちは遠慮がちだった部下も、数週間後には自分から「少し相談したいことがあるんです」と言うようになったのです。
Aさんは言います。
「特別なスキルより“話しかけてもいい時間”をつくるだけで、チームの空気がまるで変わりました。」
相談される上司とは、特別なカリスマ性を持つ人ではなく、小さな安心を積み重ねる人なのです。
よくある誤解Q&A
- 相談されると“なめられる”のでは?
-
むしろ逆です。相談されるということは、信頼されている証拠です。上司の役割は“解決者”ではなく、“一緒に考える伴走者”だと捉えましょう
- 部下に合わせすぎると“甘やかし”にならない?
-
「聞く」と「迎合する」は違います。話を聞いたうえで、「じゃあ次はどうしてみようか」と本人の考えを引き出すことが大切です。
- リモートワークで相談が減った場合は?
-
雑談のきっかけを意図的に作りましょう。オンラインでも「雑談チャット」や「5分のカメラオン雑談」を週1で設けるだけで、コミュニケーションの頻度は確実に上がります。
まとめ|相談される上司は、“答えを出す人”ではなく“一緒に考える人”
部下が相談してこない理由は、怠慢でも反抗でもなく、「相談しづらい空気」が原因です。それを変える鍵は、上司の最初の反応と、日々の小さな行動にあります。
- 否定せずに最後まで聞く
- 雑談の中の小さなサインを拾う
- 相談後に声をかける
この3つを意識するだけで、相談の数も質も変わります。相談される上司とは、答えをすぐ出す人ではなく、安心して話せる場をつくる人です。そしてその姿勢が、チームの信頼を高め、あなた自身のマネジメント力を一段引き上げてくれるでしょう。